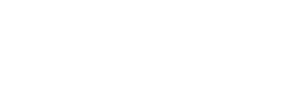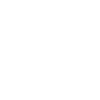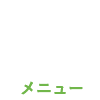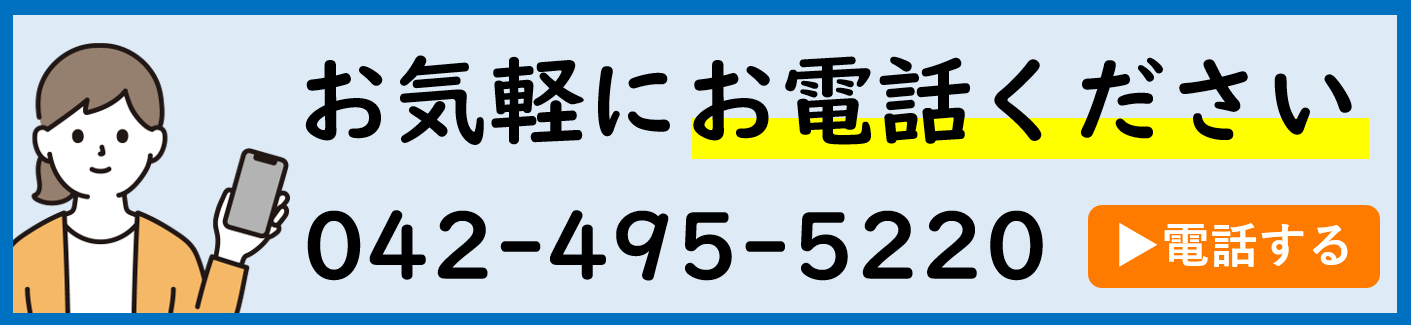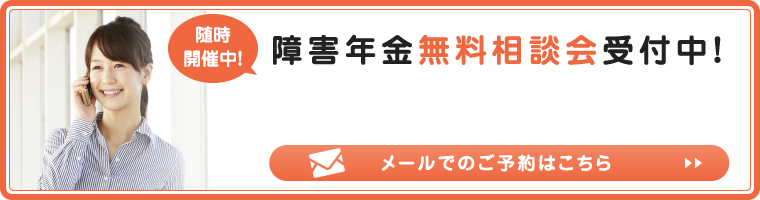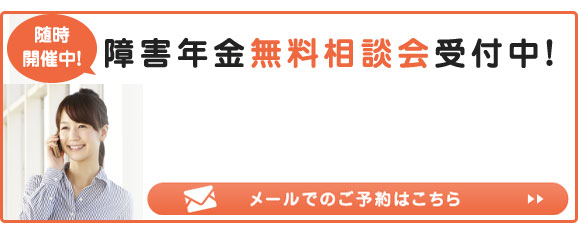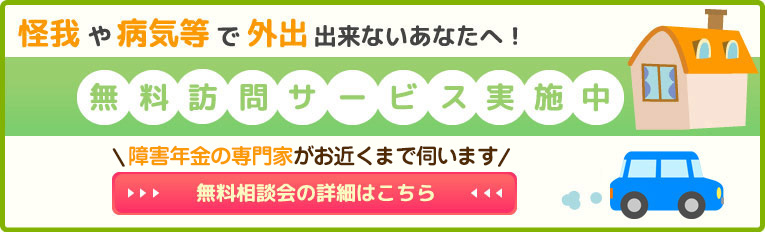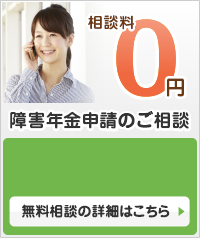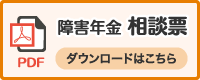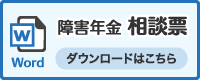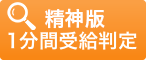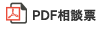障害年金の申請を自分でするには?手続きが難しい場合の対処法を解説
質問
障害年金は自分で請求できますか?
答え
 障害年金は、保険料納付の条件を満たし障害の状態が一定の基準に該当すれば、ご本人や委任状によりご家族なども請求手続きができます。
障害年金は、保険料納付の条件を満たし障害の状態が一定の基準に該当すれば、ご本人や委任状によりご家族なども請求手続きができます。
何度か年金事務所に行くことになりますが、具体的な手続きなどは主に次のような流れで進めます。
障害の程度を判断する認定基準は年金機構のホームページで公表されています。
具体的な請求の手順
1.初診日を調べ確認する
請求するためには、病気やけがのために初めて病院を受診した日付を確認する必要があります。
その場合、診断名の明らかになった医療機関が初診とは限りません。具合が悪くなって初めてかかった医療機関を初診と判断されることはよくあります。
請求する前提条件として、病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)に65歳未満であって、初診日より前に一定期間の年金保険料を納めていることが必要です。一定期間には免除や納付猶予の期間も含まれます。
例外として、初診日が20歳前であって年金に加入していない場合は、納付については問われません。また、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が変わります。
2.年金事務所で年金保険料の納付状況を確認し、請求に必要な用紙を受け取る
初診日より前の保険料納付の条件を満たしているかどうかは、年金事務所で調べてもらうことができます。保険料納付の条件に問題がなければ、請求に必要な書類一式を受け取ります。国民年金だけの加入の場合は市区町村の窓口でも可能です。
基本的な請求用紙には受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書などがあります。
3.受診状況等証明書と診断書の作成を医療機関へ依頼する
受診状況等証明書は病気やケガのために初めて受診した医療機関で受診したことを証明してもらう書類です。初診日に通院していた医療機関に作成を依頼します。初診と診断書を書いてもらう医療機関が同一である場合は不要です。
受診状況等証明書の準備ができてから診断書の作成を医師に依頼します。診断書は傷病等で8種類に分かれており、いつの時点の、どの診断書が必要かについては、事前に年金事務所で確認します。
障害年金は書類審査であり、提出した書類の内容ですべてが決まります。
どんなに症状が重く日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ意味がありません。
診断書に、ご自身の実際の症状などが反映されているか確認することが大切です。
4.病歴・就労状況等申立書の作成と、その他の証明書等を準備する
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書と並んで重要な書類であり、自己申告として自分で作成するものです。
病歴・就労状況等申立書には、病状によって日常生活でどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを、具体的にしっかり記載することが大切です。また、診断書と病歴・就労状況等申立書の記載内容や症状の程度に矛盾がないか忘れずに確認します。
その他の証明書等の書類は、家族構成などで一人ひとり異なるため何が必要かは年金事務所で説明を受けます。住民票など有効期限のあるものは診断書が完成してから準備します。
5.年金事務所に請求書一式を提出する
請求書を提出する前に必要な書類はすべて揃っているか、空欄や誤記は無いか見直します。提出した書類に不備があると修正のために返されたり審査が遅れることになります。
また、年金事務所に提出する前にすべての書類をコピーし手元に残しておくことが大切です。
提出後、概ね3~4か月で日本年金機構より結果の通知が届きます。
自分で手続きするのが難しい場合

障害年金の請求は、年金事務所で相談しながら自分で手続ができることに越したことはありません。
しかし、複雑で多くの書類が必要なため請求手続が難しいと感じる方や、体調が優れず年金事務所に何度も足を運ぶのは無理だとお考えになる方もおられると思います。
障害年金の請求手続きが難しい主な理由
・病院をいくつか転院していて、現在の傷病の初診日がどの病院かよくわからない。
・診断書を見ても、どこに記入漏れや間違いがあるのかわからない。
・診断書に自分の実際の症状が反映されているのかどうかあまりわからない。
・病歴就労状況等申立書をどのように記入したらいいのかよくわからない。
これらの難しい点は、費用は掛かりますが障害年金専門の社労士に依頼することで解消できます。
自分で何度も年金事務所へ行くのが難しい場合や手続きに不安がある方は、障害年金の請求手続に慣れた社労士に依頼することも選択肢のひとつです。
精神疾患による障害年金請求で不支給決定や低い等級に疑問のある方へ
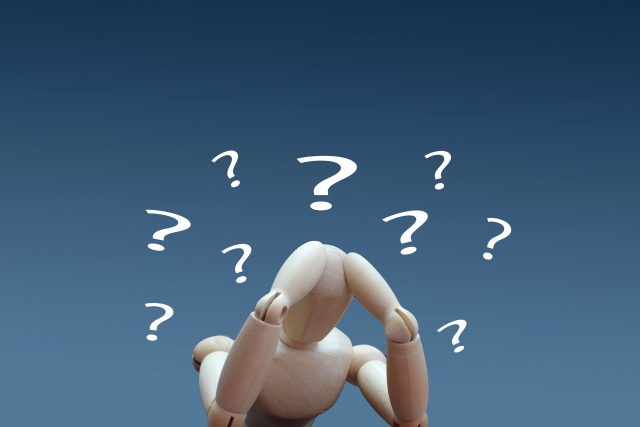
ご自分で請求して不支給や思ったより低い等級となったがどうしてなのかわからないという場合には、診断書の内容が障害等級の基準に達していないことが主な理由として考えられます。
例えば、
・医師は限られた診察の時だけしか診ていないため、患者の日常の生活をよく知ることが出来ない。
・患者も日常生活で症状により支障のある内容を医師に伝えていない。
もしくは正しく伝えることができない。
・単身での日常生活能力を前提とした診断書であることをよく理解されていない。
このように、実際の症状が正しく反映されずに不支給となったり思ったより低い等級となることがあります。
そうならないためには事前によく準備しなければなりませんが、専門家のアドバイスを受けることも大切なことです。
当事務所では、障害年金を専門に取り組んでいる社労士が的確にアドバイスできますので、気軽にお問い合わせください。
自分で申請して不支給になってしまい、当事務所に依頼された事例
ケース1【解離性障害】自分で請求したが不支給となって相談を受けた例
傷病名:解離性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 2級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約200万円
相談時の状況
ご自分でご家族や年金事務所に相談しながら書類を作成して手続きをしたものの不支給となったため、何とかならないものかと悩み、ご相談に来られました。
すでに審査請求の期限を過ぎていて不服申し立てはできないため、現在の病状で再請求となることを説明してご理解いただきました。
かなり前から不眠や不安な症状は続いていたようですが、現在は休職中で外出もなかなか困難な状態で、ご家族が家事や身の周りの世話をされているとのことでした。
受任から請求までのサポート
病状や日常生活状況を詳しくお聞きすると、解離性障害だけでなく抑うつ状態もかなり重い症状であり休職もされているため、2級以上に該当すると思われました。
不支給となった診断書を拝見すると、実際にお聞きしている症状や日常生活状況よりも、かなり軽く判定されていました。
新たに診断書を依頼するにあたり、ご本人やご家族から日常生活上の支障などをメモで非常に細かく具体的に書いていただき、整理して診断書作成ための参考資料を作成しました。
主治医にご本人やご家族から日常生活の状態を参考資料と併せて伝えていただき、抑うつ症状も強いことを追加で記載していただくことができました。
ケース2:【網膜色素変性症】自分で請求して不支給となり、相談を受けた例
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から次回更新月までの3年間の総受給額:約233万円
相談時の状況
何年か前にご自分で請求し不支給となっていましたが、やはり納得がいかずもう一度請求したいということで相談にこられました。その当時と視力などの症状はあまり変化がないようでしたが、働くこともできず家の中でもご不便な様子がよくわかりましたので、お力になりたいと思いお受けしました。
受任から受給までのサポート
前回請求時の資料は何も残っていなかったため、情報開示請求ですべての資料を取り寄せることから始めました。取り寄せた当時の診断書を見ると指定の検査方法による検査結果の記入がなかったことがわかり、診断書を作成したかかりつけの眼科医の理解を得て、改めて大学病院で検査し認定基準に沿った診断書を作成して頂きました。結果、受給が決まり大変喜んでいただけました。
年金事務所や市役所では手続きに必要な書類が揃っていれば受付しますが、立場上、受給できる内容かどうかは見ません。やはり、事前に専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
【簡単】1分間無料判定
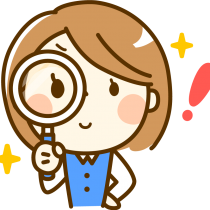 障害年金は多くの方がもらえる可能性がある年金です!
障害年金は多くの方がもらえる可能性がある年金です!
ここではご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えます!